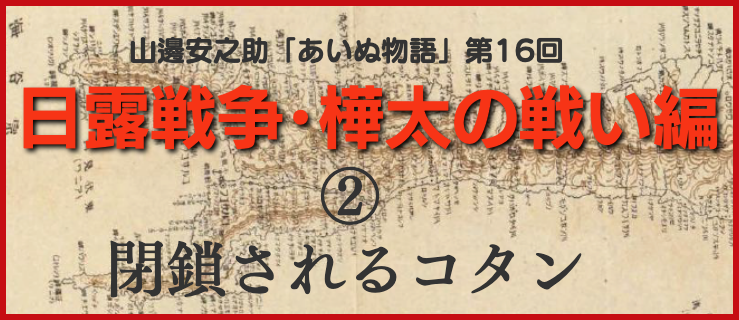
閉鎖されるコタン
内通を恐れて出入り禁止、反発した男たちは
明治37(1904)年2月8日、旅順港攻撃から始まった日露戦争は、37年の間は旅順を巡る戦いに終始しました。海軍は2月24日から旅順港の港口を塞ぐ作戦を始め、これに呼応して陸軍は8月から旅順要塞への総攻撃を開始しました。
しかし、8月の攻勢は失敗し、10月にも総攻撃が行われましたが、日本軍は多大な犠牲を出して終わりました。そして12月に入って二〇三高地をようやく占拠し、ロシアの守備隊を降伏させました。二〇三高地は旅順港を見下ろす小山でここを手中に収めると港に砲弾を雨を降らせることができたのです。
旅順攻略の原動力は、第三軍第一師団に代わって11月から投入された旭川の第七師団で、この功績により第七師団は最強師団と言われるようになります。
旭川第七師団は屯田兵後備役を主体にした師団で、寒さでの闘いに慣れていたこと、屯田兵時代を含めて長い教練の経験があり、練度がずば抜けていたこと、そして何よりも勝利を勝ち取って自らの存在を示したいというモチベーションに溢れていたことが勝利につながりました。
この後、日本軍はロシア主力を追って北上して3月1日に両軍主力が相まみえる奉天会戦を迎えます。ここでも第七師団が抜群の活躍を見せました。最左翼に配置された第七師団を主力とする第三軍がロシアの右翼を崩して敵を総退却に追い込んだのです。この戦いで第三軍司令官の乃木希典は名将の名をほしいままにしました。

爾霊山(にれいざん)は二〇三高地のこと。第七師団が山頂を攻め落とした状況を示す戦闘図(赤がロシア・青が日本)/参謀本部編『明治卅七八年日露戦史 第6巻』1912年
3月15日、日本軍は奉天城に入城して会戦の勝利を確定させますが、これまでの戦いで多大な犠牲を払ったため、北に逃げたロシア軍を追撃する体力はありません。
陸の戦いは奉天に陣取る日本軍と北の陣を敷いたロシア軍とで膠着状態に陥りました。一方、ロシアは海から戦局を変えようとヨーロッパに配備していたバルチック艦隊を派遣し、5月からかの日本海海戦が始まります。
アイヌ民族として初めての自叙伝、山邊安之助『あいぬ物語』第六章日露戦争第二節怨恨は、このような情勢を背景にして明治38(1905)年の春から始まります。
遼東半島で戦われていた戦火はまだ樺太には及んでいないものの、安之助が暮らす平和な冨内村もロシアの制はいかにあったため戦時体制下に置かれます。

あいぬ物語 (16)
樺太アイヌ 山邊安之助著
文学士 金田一京助編
六 日露戦争(上)
(二)怨恨
こうして三十八年の春になると、ロシアの人たちのいうには、
「日本の軍隊が、いつどこへやってくるか知れないから、今から無闇に勝手なところへ出かけて行ってはならない」
こう言って、富内村に五〇名の守備隊を置き、それからは毎日、朝々に村のアイヌを一か所に集めて人数を調べ、ロシアの里程で一里以外へ遠くへ行くことを禁じ、『もし一里以上他所へ出かけたのがあったら殺してしまう。それから、留守居をしたものも一緒に殺してしまう。だから、それでもよろしいと思うものがあったら、どこへ行ってみるがいい」といいながら
「その時は、こうして殺すぞ」
といって、顔先へ拳銃を突きつけて、アイヌを刺し殺す真似をした。
村の人たちは恐怖して、一同どこへも遠くに行くこともならず、一つの所へ小さくなっていた。
私の考えるのに冨内村のアイヌの人たちは、昔から日本の人と一緒になっていたものがたくさんあるし、また北海道の方から渡ってきたものもいるものだから、日本人へ内通はせぬかと気遣って、こんなことをしたのであったろうと思う。
それから、またいろいろな獣を狩りするために一同鉄砲を一丁ずつ持っていたのまで全部取り上げて、火薬も丸もことごとく没収された。
その上に魚を漁するにも、家の前の魚だけ獲れという。また薪を採るのでも、家の向こうにある木だけ採れという。
このような牽制は古来例のないことであるから、村の人達一同恐ろしくて恐れ慄いて、いつどのような目に逢うために、今こんなにされるのだろうと人々談じ合って怒み恨んでいた。とうとう
「あまりこんな牽制ばっかりハイハイうなずいていては際限がないし、こんな下級な役人風情に何をいったってつまりやしない。それよりは誰かコルサコフにある一番の大将の許へ行って直接陳情するが良い」と一同そういって激高しながら議決した。
それをば東内忠藏、何も何も考えずウッカリ守備隊長のいる前で行ってしまった!
「俺ら一同何の悪いこともありもせぬのに、どうしてこんなひどい牽制をするんだい? 俺ら明日誰かロシア語のできるやつを大泊へやって、上長官へ直訴して、少しでも穏やかにしてもらうようと思っているんだよ」
と言ったから、隊長はいよいよ警戒を厳にし、一人でも行こうとするならば、大泊へ出ている間、キムナイ駐在の人々にも申し合せて、行こうとするものがあったら、そのところで殺せと命じ、なおまた富内村にいるアイヌもあわせて殺せと命じ、村の人たちを脅しつけたから、人々恐れて縮み上がり、夜にでも昼にでも憂苦に満たされて、夜の目も眠れずに恨みを重ねた。
それでも飽きたらずに今度は漁場にある船の数残らずトーキナイの方へ持ち去って、持ち去らない破船をば火をかけたり、壊したりしてしまった。
私達皆、腸が煮え返る心持ちがした。
やけになって櫂は山の方へ隠し、錨は蔵の中の藁の積んだ下に隠した。ロシア人が来て
「櫂はどこにあるか?」
「それから錨はどこにあるか?」
と言っているけど「知りません」「知らないよ」と言ってやった。ロシア人奴らむか腹を立てて
「アイヌは一人残らず殺してしまう」と怒っている。それでも私たち一同は「知りませんな」と答えて、
「日本の人達が、どこへ隠していったんだか知りやしない」といい
「我々はいちいち見ているわけでもないんだから、どこなり勝手に探してみるがいい」と言ってしらばっくれていた。そのうちに藁の下の錨も、山のほうに隠した櫂も見つけられた。
しかし、私たちが隠したものだとは気づかずに、「ニッポンスキー、ここかくした」と言っていた。
(三)女達の結束
ロシア人の暴虐はこれだけに留まらなかった。
「お前らはそう我々の言うことを聞かないのならば、明日、男たちは皆縄をかけて大泊へ引っ張っていくからそう思え!」と厳命を下した。
村の人々は再び恐怖をして、ロシア人を怨嗟した。
「どういう訳でそんなことをするのか?」
「我々にどういう罪があるのか?」
「お前らが良くないから皆を捕らえて牢屋へぶち込むんだ」と言う。そこで私達は、
「もしそんなことをするならば、後に残る女子どもや子供らはどうするのだ」と言う。
「男たちが居ればこそ、その力で子供や女が食っていかれるのではないか? 男たちがみんないなくなったら後に残る不憫なものはどうやって食っていかれると思うのか? ロシアの役人から子どもや女たちに食をあてがってくれるのなら、我々のことはなんとされるともよろしい」と言ったら、守備隊長の言うには
「ロシアの立派な役人達の食物さえも欠乏しておる。お前たちの家族などに食わせることは役人達が許しはしない」と言う。
「そんならば、我々の家族は餓死して死んでしまっても構わんというのか?」と言ったら、ロシア人どもは仕方なく行ってしまった。
その後で女たちへ言って聞かせて、女たちへ後でロシア人がまた来たおりには、こう言えよ。
(男達を皆引っ張っていって牢屋入れた後に、私たちはどうして食っていったらよかろう? 隊長からでも食物を下さるんでなかったなら、いよいよ腹が空いて死ぬばかりだ。そのくらいなら私たちも男達と一緒に牢屋へなりと連れて行ってくれ!)
そう言へと、女たちもそう教えておいた。
そして夜になったら、ロシア人らがまた来た。その折もまたアイヌ一同引っ張っていくという。そこで女たちが私が教えておいたように言った。するとロシア人はこういった。
「女や子供を連れていくことはそりゃない」と言う。女たちが、
「私たちをば連れていかないといったって、何が何でも一緒についていく」と言う。ロシア人は
「そう女たちが連れて行けと言ったって、我々は縄をかけて放って行くまでだ」
と言って、また舟を用意しようとて帰ってしまった。
帰った後で女たちは非常に興奮して、こんなことを口々に言っていた。
「こうして明朝、本当に男たちを連れていくというならば、私たちは皆、小さい子供もらをおんぶして、何が何でも船へ一緒に乗って沖へ出ていってやる」と言っていた。
「ロシア人の奴らが見て手荒なことをするようだったなら、本当に暴虐なことをしてくるようだったら、殺されたって構はしない」そういって激高しきっていた。
それなりに夜が明けた。けれども、ロシア人も男たちを連れていくとも、なんとも、もう言わずにそのままになった。
なおこの連載は河野本道編『アイヌ史資料集 第6巻 樺太編』(1980・北海道出版企画センター)に収録された『あいぬ物語』(1913・博文館)初版の復刻版を底本にしています。原文は大正時代の忠実な復刻で旧漢字旧仮名遣いであり、当サイトに掲載するにあたって、読者の皆さまの読みやすさを考慮して、旧漢字を新漢字にする、現代では用いられない漢字を平仮名にするなどの調整を行っています。なお『あいぬ物語』は青土社より新装版が出ています。
























