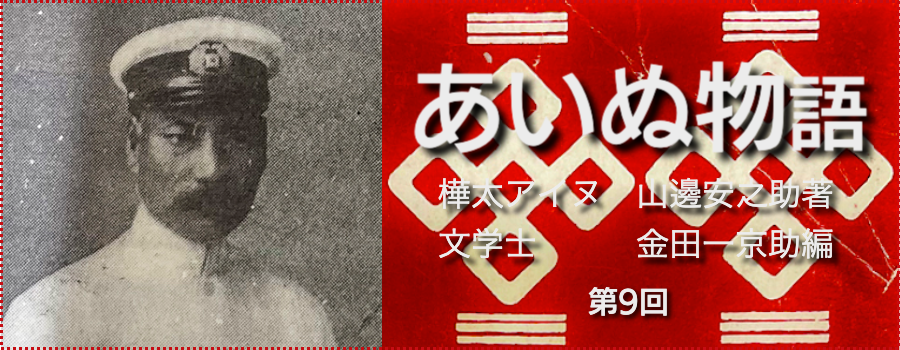
帰郷の決意
安之助は宗谷海峡を渡る
疫病により多くの犠牲者が出たあと樺太アイヌ移民のコタンは火が消えたようになりました。そうした中で、安之助は子供の頃に離れた故郷を訪ねようと決意します。官に許可を求めると、拍子抜けするほどあっさりと簡単に許可が出ました。
あいぬ物語 (9)
樺太アイヌ 山邊安之助著
文学士 金田一京助編
四 帰郷
(一) 扁舟
石狩の漁場には、 魚がまだ沢山取れるし、私たちは何一つ不足な事もなく暮らしていた。けれども国から一緒に出てきた親しい人たちが皆世を去ってしまってから、何の楽しいこともなくなって、小さい時に振り棄ててきた故郷が懐かしくなった。
その上、お祖父さん、お祖母さんも、みんな一緒に眠っておられる故郷の地、その東海岸には、遠いけれども縁続き人たちもなお残っているように聞いている。
どうしておられるのであろうか、そのことさえわからないのであるけれど、私などは国の事は夢のようにしか知らないが、年寄りから聞けば川には魚が溢れており、海にも同様、魚が溢れているそうな! 一度でも自分の故郷にどんな人達がいるのか見てみたいような気がする。
そこで石狩からはるばる函館にあった役所へ行って、私ども一同郷里の先祖の墓参りに行きたいから、旅行免状を下附していただきたいと願ってみたら、案外容易に免除が下りた。
それから明治26年の8月の月、雷札の村を去って、樺太へ帰る支度をした。その時の同行者は私の家内と私の子の八代吉、それから内友の昔の頭領の後裔の内藤忠兵衛とその家内と娘の芳子、それから 雲羅宇志計(ウンラウシケ)という人(この人は後に真岡へ行って亡くなった)。
なお他に年寄りが3人いた。1人は胡蝶別の昔の首領の後胤で、1人は淵瀬遠渕の人で、今1人は皆淵の人であった。
この人数全て、私とともに13人で川崎船一隻に色々な漁具や米などを積み込んで石狩川の口を出た時は、8月の13日であった。
13人の中から老人2人と女や子供等を除いた残りの4人の男が舟子となった。その4人の中で内藤忠兵衛がが最年長者の故をもって船長となり、あとの吾々3人の若者が水手となった。
初めて出かけた日は浪もなく、風がよかったからずんずん進んだ。翌日には増毛へ着き、その翌日には築別へ着いた。少し浪気があったから、築別川に船を入れて、2~ 3日ほど日和を見合わせた。
それから出発して天塩川へ船を入れ、ここに一夜を明かしして、翌日宗谷の稚内に到着した。それから昔の会所前と言う所へ船をつけた。
(二) 難船
ここからいよいよ宗谷海峡の荒汐を乗り切らねばならない。そこで8日の間、日和見をして8日目にいよいよ乗り出した。
途中から風が悪くなって浪が荒れるから、船も進むことができない。途中からい一先に引き返し、宗谷の灯台の下の 左内というところに1日暮らして、明くる日、また出かけて行ったが、今度は 霧が深く降りて、さらに先が見えない。
能登呂岬へ船をつけようと思ったが、誤って能登呂の外海へ出て、白主村の方へ行ったのであった。
それから逆にまた船を引き返して、能登呂の崎をぜひとも回ろうとすると浪のために能登呂の鼻へ打ち付けて接岸したが、その岬角の岩の上へ船が上がって粉々になった。
この時の辛苦艱難は譬へんに物なしで、私は述べ切れないほどであった。
自分の体ひとつはどんなにでもして上がろうとすれば上げられる。けれども元より船の中の人々は、自分一人助かろうとは思わない。目の前で自分の妻や子供の死ぬのを自分のみ、どうして生きられよう。そこであらん限りの死力を尽くして、女たちは子供等をやっとのことで陸へ救い上げた。
それから沈んだ船の中の荷物や米などを死力を尽くしてあげた。その中には塩など水に浸かってしまったものは皆うっちゃって、そして人々一同やっと命からがら砂浜へ上がった。
そこで初めて懐かしい故郷の地を踏みには踏んだが、気も体も疲れ果てて動く事もできなかった。
なおこの連載は河野本道編『アイヌ史資料集 第6巻 樺太編』(1980・北海道出版企画センター)に収録された『あいぬ物語』(1913・博文館)初版の復刻版を底本にしています。原文は大正時代の忠実な復刻で旧漢字旧仮名遣いであり、当サイトに掲載するにあたって、読者の皆さまの読みやすさを考慮して、旧漢字を新漢字にする、現代では用いられない漢字を平仮名にするなどの調整を行っています。なお『あいぬ物語』は青土社より新装版が出ています。
























