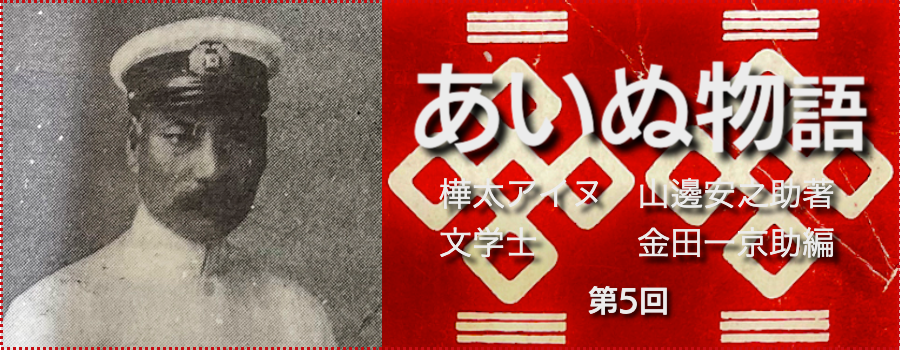
アイヌだからといって差別をつけてはいかん!──西郷従道
働き始めた安之助が見た和人
明治8(1875)年の樺太・千島交換条約によって樺太から現在の江別市対雁に移った樺太アイヌ・山邊安之助。対雁での興味深いエピソードが語られています。
対雁の学校を修了した安之助は、まだ勉強を続けたいと恩師道守先生の紹介で、働きながら学ぶことのできる幌内の商店で丁稚奉公をします。そのときの給料は5円は現在の貨幣価値に直すと26万円相当です。貯金に勤しんで学費を貯めますが、結局かなわずに石狩の「共済組合」から声がかかり、漁場で働くことになりました。
この共済組合は明治15(1882)年7月にカラフトアイヌ移民の授産のために設立された「対雁移民組合」です。安之助はここでの労働が「金がたくさんもらえるのが面白い」ので進学のことを忘れてしまったと書いています。
「対雁移民申合定款」によればその棒級は「伍長3円以下」「副支配人8円以下」「支配人10円以下」を「其月15日前後の別を以て全額又は半額を給すべし」(『石狩市史・中巻』53p)とあります。面白ほど儲かったという安之助の証言からすると現代換算で月給41万円相当の副支配人以上だったのでしょう。
のちの「歴史書」によってこの対雁でカラフトアイヌ移民は迫害の限りを受けたという印象を持ちがちですが、実際は同時期の和人入植者よりもはるかに厚遇されていました。
そして、西郷従道と開拓判官松本十郎の珍しいエピソードを紹介しています。明治政府の重鎮・西郷従道のエピソードは、対雁の樺太アイヌのコタンを訪れて宴会を催したというものです。

西郷従道
西郷従道は西郷隆盛の実弟で元帥海軍大将にまで上り詰めた人物。この時は、黒田清隆が開拓使長官を辞めた後、暫定的に開拓使の長官を務めていました。アイヌの人々と楽しく交流をする西郷を、後の北海道長官永山武四郎が「みっともない」と誡めますが、西郷は「アイヌだからからと言って差別をつけてはいかん!」と言って叱責します。
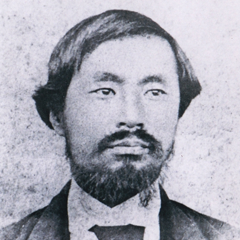
松本十郎
また松本十郎判官では、横柄な態度の巡査を諫めるために、自身が浮浪者のような姿をしてわざと巡査の注意をひき、注意を受けた後に身分を明かす、という遠山の金四郎ばりのエピソードが語られています。
これらエピソードは、開拓使とそれに続く三県時代において。官がどのような姿勢でアイヌ民族と向きあってきたかを教えるものです。従来の認識を覆す貴重な証言ではないでしょうか。
なおこの「樺太アイヌ北海道移住」については当サイトで取り上げています。下記リンクを参照ください。
なおこの連載は河野本道編『アイヌ史資料集 第6巻 樺太編』(1980・北海道出版企画センター)に収録された『あいぬ物語』(1913・博文館)初版の復刻版を底本にしています。原文は大正時代の忠実な復刻で旧漢字旧仮名遣いであり、当サイトに掲載するにあたって、読者の皆さまの読みやすさを考慮して、旧漢字を新漢字にする、現代では用いられない漢字を平仮名にするなどの調整を行っています。なお『あいぬ物語』は青土社より新装版が出ています。
あいぬ物語 (5)
樺太アイヌ 山邊安之助著
文学士 金田一京助編
二 流転──帰化新附の民
(六)立志
道守先生が学校を去られた時に私も学校を出てしまったけれど、 私は何とかして今少し勉強したいと思っていたから、友達の市来善助と二人で道守先生へ行って話した。すると、道守先生は門馬武という方へ私たち二人を預けられた。
その門馬という方は三春県という所のお侍で、元は二本差しにお侍様だと側いうことで道守先生のお友達であった。ちょうどその時は幌内炭鉱の側の市来尻という所の切開きの時で、そこへ人夫がどしどし入り込んだ。
門馬氏は、そこへ大きな商店を建てられた。私たち二人はその商店の奉公人となって夜分に仕事が済んだ時に、仕事の合間合間に本でも教えてもらってかたがた商売上のことも覚えたらよかろうと、そう先生が考えられてその店へ預けられたのであった。
私たち二人もそのつもりで喜んで行った。
しかるにその商店はいわゆる士族の商売で、あまりに大雑把すぎてたちまち失敗してしまった。そして主人は国へ帰ってしまった。
その後、店は番頭の中村熊吉という人が預かって留守居をしていた。私たち二人は最初の目論見がすっかり外れて落胆していたが、そのなかに市来一人は石狩の方へ帰って漁の手伝いをするようになり、私一人はなお踏みとどまって何か良い工夫がないかと考えていたが、番頭さんの弟に作太郎という人の弟に私と同年の子供があった。
私と一緒に越後へ行って、内地の学校へ入ろうという相談を決めて大喜びしていた。私は、どうにかして越後までの旅費を欲しいと思って、1ヵ月に5円ずつ給付金をもらうのを一文も使わずみんな貯金をした。足りないところは労働をして1日80銭ずつもらって一生懸命働いていた。毎日内地の学校へ行くことばかり考えて暮らしていた。そのところへ石狩の共済組合からぜひとも漁場へ来て働くようにといって手紙が来た。
私はがっかりしてしまった。けれどもアイヌ一同のいうことに違反しては悪いと考えたから、嫌々ながら石狩へ出て行った。それから以来、漁の労働に取り掛かって金がたくさんもらえるのが面白いので打ち紛れて終わり、勉強の機会を失ったままになってしまった。
(七)西郷中将と永山大佐
対雁にいる間いろいろな面白いことがあった。明治16年の頃でもあった。故西郷従道侯が私たちの村へ見えられて、アイヌを数多く集められて、アイヌ一同と親しく酒肴を賜った。その時侯爵は大杯を引いて酒をアイヌに飲ましめ、侯爵もまたアイヌ達から大杯を受けて飲まれた。
そしてアイヌ達がだんだん酒が回ると、公爵もそろそろ陶然となられた。やがてアイヌ達が手を打ち舞踏を始めたところが、公爵、興に乗じてアイヌの群中に入って一緒に手を叩き、舞踏を始められた。
その時、公爵の同道の永山武四郎といって後に北海道長官になられた方が見てこう言われた。
「陛下、いやしくも開拓長官ともあろう方が、どうしてこんなアイヌ風情のものと一緒になって踊ったり、跳ねたり、酒を飲んで狂い回るというようなことをなされますか? そんなことをされては他所の見る目もあり、体面上よろしくないと私は考えます」
ところが侯爵は一向に無頓着で
「何を汝は言うんだ。アイヌと一緒に踊るのは悪いと言うのか? そんなわけはないじゃろう。アイヌじゃとて日本の臣民じゃ! 陛下の赤子じゃ! しかるにお前は何を言っとるんじゃ!? アイヌだからからと言って差別をつけてはいかん! お前の考えが違うとるんじゃないか」
そういってどうしても大佐の言葉を聞き入れない。
永山大佐もなかなか負けてはいない。一人がそうじゃないと言うと、また一人がお前の言う方こそいけないと言う。とうとう激論になって双方いがみ合いの姿となり、帽子を脱し、上着なども脱いでしまって、 夜明け近くまで大喧嘩を始められた。
永山大佐はしまいに憤然として「じゃあ勝手にしろ! おらァ知らん。帰る」 と言って馬に乗って札幌へ帰ってしまった。そこで私たちはこれァ後にどうなることであろうと思っていた。
西郷侯爵は翌朝自身で永山大佐の方へ出かけられた。
「昨夜は二人で大変激論したの! お前も、なかなか強情な男じゃな! じゃが彼の位くらい強情ならたくさんじゃ」
といって褒められたという話であった。それから中山大佐は西郷侯爵にすっかり気に入られて、ズンズン出世され、後には北海道長官にまでなられた。
(八) 松本(十郎)判官
その頃、松本(十郎)判官という名判官が居られた。私たちが対雁へ来てまもなく、まだ何も知らなかった頃に、川端の砂原で遊んでいると、その判官が10銭銀貨を懐から出して、一つずつ皆の子供へ配られた。私はどういう善いものだかも知らなかったが、初めてピカピカ光るものをもらって面白かったことを記憶している。
当時、北海道では役人が非常に威張ったもので、 今でいう巡査、その頃は邏卒といった人たちは樫の棒を家手に持って巡回した。その当時の邏卒と言ったらそれは酷い恐ろしいものであった。石狩あたりの人民はそのために泣いたものであるそうな。
松本判官がそのことを耳にしてたいそう心配して、自分で労働者に身を扮し、山刀などを腰に下げ、木を切るようなふりをして山の中に徘徊された。山林局の役人がそれを見つけて
「何しに山の中を歩いているか?」
果たして非常にやかましい。その時松本判官が平謝りに謝って詫びるけれども、なかなか許さない。その上に今度は、
「お前の名は何と言うか?」
と問い詰める。けれども判官は名は、明かされぬから言わずにいると
「じゃ家はどこか?」
と問う。
それでも言わずにいるものだから、家へ引っ張っていこうとする。松本判官は、はいはい言いながら役人と同道する。
だんだん行って家続きの街の方へ来るので、山林の役人が、この奴どこへ連れて行くんだろうと思いながらついていくと、松本判官の邸へ入る。役員、心の中で怪しみながらついて這い入ると、 判官、着物を脱ぎ替えて、本当に自分の着物を着て山林の役人を招いた。そこで延々説諭をされた。
また、あるときには判官、酒を飲んで酔っ払いの真似をして路傍に寝ていた。巡査がきて見つけたが、判官とは知らないから、普通の人間を叱りつけるように叱りつけて起こした。
「 起きろ! 起きろ!」と言いながら警棒をもってつついた。
けれどもなお眠ったふりをしていたので、巡査は怒って土足のままで足蹴にして起こした。松本判官、起き上がると巡査、
「お前の家はどこだ? 家に行って寝ろ」と言う
で判官は巡査もろとも家へ行き、そうして前にやったように自分の家に連れ込んで巡査をこんこんと御諭された。
「今後とも酔っ払いがあろう。どんな人間にせよ、よって道路に寝ているとも決してこのようなことをしてはならん。懇切に探り起こして、家を持っているものなら、家を送るがいい。決して棒などでつついてはいけない。また足などで蹴ってはいけない。そんなことをしなくたってよく言って聞かせればいいんだ。今お前がしたようなことをしては誠によろしくないぞ」
と松本判官にさとされた。
それ以降、役人たちが目を覚めて普通の人をあまり乱暴には取り扱わなくなって、今日までよく人々をいたわり世話するようになった。






























