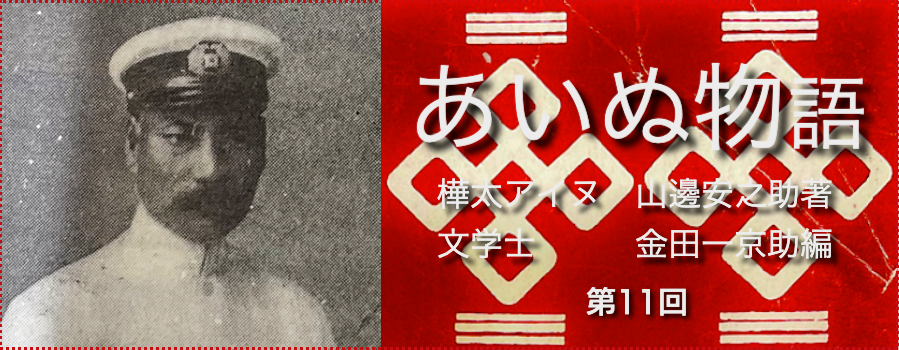
18年ぶりの富内村
安之助は故郷に帰る
九死の一生の想いで樺太に戻った安之助一行は、ロシアの官憲に捕まりました。親切な和人の助けによって一行は救われ、故郷を目指すために南樺太の中心都市・大泊(現コルサコフ)に船で向かいました。街はすっかりロシア化されています。桟橋に近づくとまたロシア官憲が現れました。一行は無事に故郷に付けるのでしょうか?
あいぬ物語 (11)
樺太アイヌ 山邊安之助著
文学士 金田一京助編
四 帰郷
(五) コルサコフ領事館
そして太泊に着いた。今桟橋のあるカルサコフという処へ行った。けれども桟橋の側に居ることをロシア人らが許さないから、わきの方へ行っていると、ロシア人が一人来て、一の沢の方へ行けという。そこでまた一の沢の方へ船を回しているのに、朝から昼過ぎるまで、そうして置かれた。
その時、一人の日本人の商人が見えた。その人は山本という人で、その頃、このカルサコフの町にある山本商店の主人であった。日本人だから、ついにはじめて「かくかくしかじかの次第でやってきた」という一部始終を物語ることができた。
すると、この人も親切な人で「そんなら領事館へ行けばいい」といいといって、領事館へいいに行った。そのおかげでやっと私達一行は桟橋の側へ来いと領事館からいわれた。
それからロシアの検疫官と、日本の副領事の鈴木陽之助という方が来て、私達の一行も一同体格検査をし、船も中まで見せ、物も一つ一つ調べて、それからやっと領事館の本館の下にある小屋へあがって、そこに居れと領事館から言い渡された。
それから四日五日ほど厄介になっていた。その時の領事は口井様というたいそう立派な方であった。私達の一行を大層を不憫に思われて、親切に取り扱われた。口井領事の言われるには――
これから余程永くこっちにいるだろうから、お前たちが持ってきた米はやたらに食べないようにせい。もしも越年中に米を切らすようなことがあっては悪かろう。今ここのところに逗留する中には、米は領事館から食わせてやろう
と言われ、それからまた領事に言われるには――
我々というものは、我国の人々が、もしもこういう難儀艱難して来るものがあった場合に、いつでもそれを救助してやるので、その職務でこの地へ来ているのであるから、遠慮は要らないから、安心しておれ
と丁寧に私たちに諭された。
時はすでに秋であったから、口井領事は内地に引き上げられるところであった。そこで後に残る人たちに向かって「アイヌを親切に取り扱ってやれ」と残されて、それからまた「越年中に米でも切らした場合には、領事館の留守の人達に行ってよこすがいい」と、そういって立たれた。
けれども、私達は越年中米を切らしもしなかったから、お願いに行きもしなかった。
思い出の郷
さて私達が今ここに着いている。そしてここから富内村の方へ行こうとしている、ということを富内村の方へ知らせてやりたいと考えていた。
しかも、私達の一行の老人の一人が山路越の近道を記憶しているというから、所用あって行く日本人一人を案内し、自ら池邊鑚(チベサニ)を経て富内村へ出かけた。
それから私達はまた漁船へ諸道具を積み込んで、大泊の港を出て、いよいよ故郷の村の方へ漕いで行った。
一八年前の昔、このあたりを船で渡した時分には、まだほんの子供であったから、なんということもなく夢中で過ぎたのであった。
今日三十近い男盛りになって、若い妻を携えて、こんな風にして帰ってきて見ると、故郷の山河が見違えて見える程、様を替えてしまって、どこへ行ってもことごとくロシアの里になっている。
船は今、恋しい、懐かしい、野満別村の沖の近くに来たけど、野満別村さえも、ことごとくロシアの里になっているのみならず、ロシア官憲がうるさいから、ここへは船も寄せずに断念して、池邊鑚へ上がった。ここはさすがに日本人の漁場もあるだけにいくらか故郷に帰った心持ちがした。
ここでアイヌの礼式で神様を拝し、この里の神様を通して我々が生まれた村の地の神様へ、こうしていよいよ帰ってきましたということを告げて、生まれ故郷の神様を陰ながら式だけ拝した。
異郷の故人
池邊鑚湖を船で越して富内村へ抜けようとしたが、湖の口が無くなって、船が入れないので陸上の諸道具を背負って運搬した。それから小さい船で何遍も何遍も渡して運んだ。
池邊鑚湖の端から富内湖の端までの間一里半余りある。ここは昔栖原家の人々が大金を投じて開いた道があった。その道路は、今なおわずかに痕跡を留めていたから、その道に従って諸道具をめいめい背負って越えていった。
その間に大木が倒れている処もあり、あるいはその後に伸びた木や、あるいは雑草などが非常に茂って大層辛苦して富内湖の外れまで死ぬような目を見てやっと着いた。
富内湖の端まで来て見ると、富内村から吾等を迎えの人々が丸木舟に乗ってここに来ていた。このときは何ともいいようのないほど嬉しかった。
その時迎えに来た人達は富内村の時朝(今の名和は上村時朝という。もと遠古丹の人であるからその遠古丹の名前を取って植村というのである)、イカサアイヌ(今の名は勝村源蔵という。この名前は日露戦争の時に、わが軍大勝利の記念に陸軍の人達からつけてもらった名前であった)、呂禮のアイヌ、宗吉及び東内忠蔵の弟、その他二人のアイヌなどであった。
この人々と逢ったときは、誰も彼も初めての対面であった。いろいろ話し合って、お互いに、ではお前はそういう人であったのか、とやっと解った。
そこで皆の人々と一所に逢って、村へ帰ったような気がした。
それから迎えの丸木舟に荷物だの、人々半数ほど乗せられるだけ乗ってひとまず行った。小さな丸木舟のことでもあるから、人々一度にというわけにはいかなかったから、私達は後に行って、湖岸に一晩泊まって、明るく日、また迎の船に人々一同乗って富内村へはじめて落ち着いた。
石狩から八月の十三日の日に立ってから、今まで1ヶ月半を旅に過ごし、やっと富内村へ着いて、この村の総代の東内忠藏の家へ旅装を解いたのは、そろそろ冬になりかかって雪などのポツポツ降りそめている頃であった。
なおこの連載は河野本道編『アイヌ史資料集 第6巻 樺太編』(1980・北海道出版企画センター)に収録された『あいぬ物語』(1913・博文館)初版の復刻版を底本にしています。原文は大正時代の忠実な復刻で旧漢字旧仮名遣いであり、当サイトに掲載するにあたって、読者の皆さまの読みやすさを考慮して、旧漢字を新漢字にする、現代では用いられない漢字を平仮名にするなどの調整を行っています。なお『あいぬ物語』は青土社より新装版が出ています。
























