[倶知安] 明治43年 鈴木重慶 アメリカ直輸入農業を始める
歴史を知ることの意味は、過去を懐かしむこと、または珍奇な興味をもたらす娯楽ではありません。歴史の本質は〝今を理解すること〟そして〝未来を見通す〟ことです。歴史を失った社会は未来を失う──と言われる所以です。今やニセコ・倶知安と言えば世界的なマウントリゾート。日本人よりも外国人の方が多いともいわれる地域は、歴史的な背景もなく、パウダースノーの魅力だけで世界のニセコになったのでしょうか。明治28年に倶知安に入植した鈴木重慶を紹介します。
■開拓者鈴木重慶、アメリカに渡る
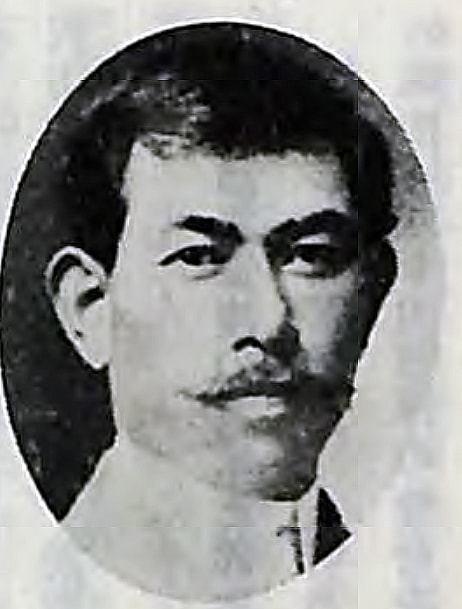
鈴木重慶(出典①)
明治28(1895)年5月、鈴木新、林原常次郎、勝田千之助3人の名儀で、山陰移住会社農場の隣接地540万000坪の貸付をうけ開墾がすすめられた。米田の敬止録にある「出雲団体」がそれらしい。
この農場の管理人鈴木重慶(鈴木新の息子)は、小作人とともに木を伐り、小屋がけをして開墾した苦労人だが、小作人に農業を教えるには、自分も勉強しなければならないと明治33(1900)年、札幌農学校(いまの北大の前身)農芸科に学び、明治36(1903)年同農学校を卒業した。
農学校を出た鈴木はそれだけで飽き足らず、明治36(1903)年、農商務省実業練習生として6月12日渡米、アメリカで当時名高ガラー農場に入って農業経営の実際を学び、練乳工場を視察したり、ニューオリンズ附近で農業や開墾の作業をした。
明治38(1905)年にはクリスタルシティ(バージニア州アーリントン郡)のフッグ氏の牧場で農業経営を研究、同年8月にはマンハッタン(カンザス州)で農家大学(カンザス農科大学・現カンザス州立大学)に入学し、農業経営学、農用機械学、酪農学を専攻、その後もアメリカ各地の牧場、酪農工場を視察して明治40(1907)年3月日本に帰った。
アメリカ帰りの鈴木は、明治40(1907)年8月東北帝国大学農科大学(後の北海道帝国大学)助手を拝命、畜産と農産製造実習を担任、同大学第一農場畜産部主任などをしていたが、43年大学をやめ、倶知安に帰ってきた。[1]
安孫子孝次(『オホーツクの幻夢』参照)は明治41(1908)年に農科大学を卒業していますから、1年間この鈴木重慶から教えを受けています。今ではほとんど語られることが無くなりましたが、安孫子孝次は、北海道を今のかたちにした功労者の一人です。安孫子孝次は琴似屯田兵の子で、開拓に苦労する両親の助けになりたいとして農学を学ぶ決意を固めました。原生林に分け入って開拓に従事した入植者であり、アメリカの農業を深く学んだ鈴木重慶から強い影響を受けたのではないでしょうか。

倶知安のジャガイモ畑(出典②)
■帝大教官を辞めて倶知安に帰郷
明治28(1895)年、鈴木新らの名義ではじめた鈴木農場は、島根県から移住、旅饗、小屋掛け料、農具、家具、種物、1年間の食糧を貸与するなどを条件に小作人を募集、開墾にかかった。
明治29(1896)年3月、各地主が地区をわけて経費を分担することにし、鈴木農区、教育興基会農区(神官教育機関)、守成会農区(美保神社保存会)横山農区、入江農区の5区にわけ、鈴木、守成会、横山3農区は鈴木重慶が管理、入江、興基会農区は入江竜雄、遠藤某が経営した。
明治34(1901)年、開墾成功検査に合格して道庁から付与をうけたが、鈴木重慶が渡米中に興基会は希望者に売却、入江農区は横山に買収された。
明治43(1910)年、東北帝大をやめた鈴木重慶は、残った土地115町歩で、アメリカ仕込みの混同農業をはじめた。[2]
富国強兵を目指していた明治大正の日本では、政府は有為な若者を官費によって欧米先進国に送りだしていました。鈴木重慶が4年に渡ってアメリカ農業を学びに留学したのは、将来の日本のリーダーになって欲しいとの政府の願いでした。帰国後、東北帝大農科大学の助手になった鈴木は、『オホーツクの幻夢』で紹介した渡辺侃のように間違いなく大学教授または道や政府の高官の階段を駆け上がったでしょう。それなのに倶知安に戻り農業を始めた。若き日に原生林で鍬を振るった記憶は博士の名誉より重かったのでしょうか。まさに開拓者精神=フロンティアスピリットです。

鈴木農場の位置
■倶知安に出現したアメリカ農場
大正2(1913)年、鈴木自身がまとめた「普通農経営法」(明治記念拓殖博覧会で銅賞を獲得)のおもなものを紹介しよう。
●農業組織の決定
①耕種組織は第一地力の増進、第二雑草の繁茂をふせぎ、第三労力の平均を得せしめんがため、左記の輪作法による。
②農場所産の穀実茎桿の一部はこれを畜産物に変じ、以って農場の収入増加をはかると同時に地力の増進土の改良をはかること。
③機械力を応用し労力の節約をはかること。
④副業として機械の余力を利用し精穀業を経営し、以って飼料を安く得ると同時に農場収入の増加をはかること。
この中でくどく言われている労力は、年雇い、没期間雇い、日雇いにわけ、日雇いは男5~60銭、女35~45銭、農期間雇いと年雇いは1農期食費のほか40円内外で雇っていた。
また輪作は6年輪作で大福豆、小豆、大麦、裸麦、ウズラ豆、トウキビ、エンバクを8区にわけ交替で植えていた。
『オホーツクの幻夢』において、北海道の輪作農業は宇都宮仙太郎と黒澤酉蔵による北方農業、とくにデンマークのエミール・フェンガーによってもたらされたと書きましたが、ここにもう一つの源流がありました。北海道における輪作農業の開発には、エミール・フィンガー由来するデンマーク系の流れと、鈴木重慶→安孫子孝次というアメリカ系の流れがあったのかもしれません。今後の研究課題です。
●建物 事務所兼農夫舎、収穫舎及び精穀所、牛舎及び鶏舎、農具庫及び殻物庫、製乳所、肥料置場、牧草小屋など。
この製乳所は精穀所に接続し、鉄管で蒸気を引き、製酪、殺菌作業に使っていた。
●家畜 耕馬3頭、牝牛15頭、牡牛1頭、犢(子牛)7頭、豚2頭、ニワトリ20頭など。
●農耕用器具 札幌製プラウ3、ハローニ、カルチベーター1、倶知安除草器2、キヤフーン氏撒播器1、木製へイレーキ、へイホークなど(のちに倶知安ではじめてのトラクターをいれた)
●製造用農機具 精穀機、石ウス、万石、クリームセパレーター、自製チャーン(バター製造機)、自製ウオーカー各1など。
エンバクの収穫にはモーアを使い、ほかの麦類は手刈りだった。
●農場の特徴
①蒸気原動器は脱穀、精穀、濃厚飼料生産など有効に使う。
②夏作の跡地は畦間に大豆をまき緑肥にする。
③牧草は河岸、農耕不適地に栽培する。
④種子は自分で撰び、麦類は黒穂病予防に塩水選とする。
⑤高価な舶来農具は蒸気原動機、モーア、播種機、ホーク類のほか使用せず。脱穀機、ローラー、ヘイレーキなどは経営者の考案で製作させる。
これによると鈴木自身が牧夫、火夫などを使って経営していた農場は30町、のこりは小作人を使っていた。いずれにしても当時の村民を驚かせたのは、蒸気原動機を利用した脱穀、精穀などのほか、アメリカ製の播種機、モーア(牧草刈取機)などの大農機具をふんだんにいれ、牛、小家畜をいれ、輪作を行なうなどの新らしい農法であった。[3]

鈴木農場のトラクター(出典③)
明治40年代の倶知安に映画「風と共に去りぬ」に登場したのとまったく同じアメリカ農園が誕生したのです。鈴木重慶は倶知安で初めてトラクターを導入したとあります。Wikipediaで申し訳ありませんが、
日本における農業用トラクターの導入は、1909年(明治42(1909)年)に岩手県雫石町の小岩井農場が導入した蒸気式トラクターと、1911年(明治44(1911)年)に北海道斜里町の農場に導入されたアメリカ・ホルト製の内燃機関式トラクターが、それぞれの日本初といわれている[3]。しかし、日本における農業機械の歴史は長らく歩行型耕耘機がそのほとんどを占めており、乗用型トラクターは第二次世界大戦後まで特殊な農場・牧場で細々と用いられるだけにすぎなかった。[4]
とあります。鈴木重慶のトラクターは導入は相当な初期です。しかも町史の写真(コピーが汚くてすみません)では、希少な乗用型です。日本のトラクター史を塗り替えるかもしれません。いずれにしろ当時の人々にとっては大変な驚きだったでしょう。
この鈴木重慶がもたらしたフロンティアスピリットが地下水脈を通じて現代に湧き出し、ニセコの世界的リゾートとして開花した、というのが本サイトの見解です。
【引用出典】
[1]『倶知安町史』1961・69-70p
[2]『倶知安町史』1961・70-71p
[3]『倶知安町史』1961・71-72p
[4]https://ja.wikipedia.org/wiki/トラクター 2020/03/25
【写真図版出典】
①『倶知安町史』1961・69-70p
②倶知安町公式サイト>観光>知安町の見どころ>じゃがいもの花情報 https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/tourism/midokoro/jaga_hana/
③『倶知安町史』1961・69-70p























